こんにちは。画家の宮島啓輔です。

今回は、「アクリル絵の具は何に描く?初心者向け:紙、キャンバス、木製パネルの選び方と特性」のテーマでお伝えして行きたいと思います。
アクリル絵の具はアートの歴史の中では比較的新しい絵の具ですが、その扱いやすさから広く普及しています。
ほぼ何にでも描く事の出来るアクリル絵の具ですが、支持体(絵の具をのせる素材)によってその性質が変わってきます。
本記事では主な支持体である
・紙
・キャンバス
・木製パネル
の3つについて特徴、選び方について解説します。
目次
アクリル絵の具で紙に描く場合
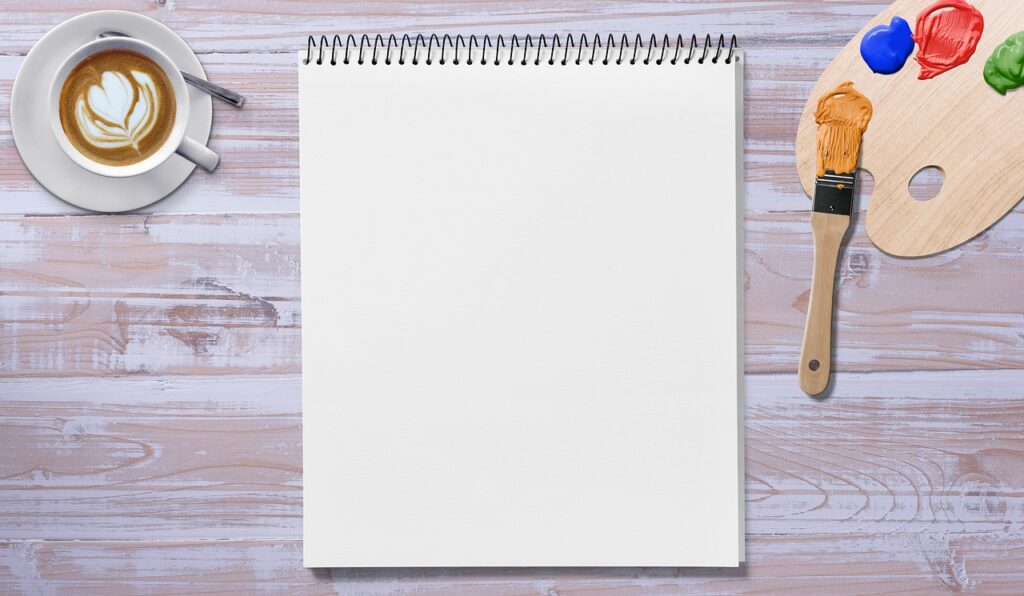
子どもからプロの画家まで幅広く使用されていて、一番身近な画材だと言えます。
紙の最大の特徴はその吸収性で、水性の絵の具であるアクリル絵の具や水彩絵の具に向いていますが、油絵の具のような油性の絵の具は紙がを痛めてしまったり、紙が油分を吸い取ってしまい耐久性も下がってしまう可能性があるので使用は控えましょう。
アクリル絵の具で紙に描く事に向いている作風
紙に描くデメリットの一つとして、木に描く場合などに比べて、耐久性が弱くなります。
まわりの臭いや水分を吸いやすかったり、力の強い描き方をした場合は紙が破れる可能性があったりするので、アクリル絵の具で紙に描く場合は水彩風の薄いタッチや滲みの表現の方が向いています。
アクリル絵の具で紙に描く事のメリット
紙に描くメリットは、持ち運びやすさと比較的安価かつ販売している店舗が多い事が挙げられます。
スケッチブックのように何枚かの紙がセットになっているタイプのものだけでなく、水多めで描いた時に波打ちにくくするための紙にまわりが接着されていて描き終わった後に外す事のできるブロック水彩紙という商品も販売されています。
ケント紙、画用紙、水彩紙など目的別の紙が様々なメーカーから豊富に販売されており、自分に合った紙を探す事ができます。
画材専門の店以外にも販売している店舗は多いので手に入れやすいです。
アクリル絵の具でキャンバスに描く場合

「画家と言えばキャンバス」のようにかなり絵画的なイメージが強く、古くから絵画の支持体として使用されています。
油絵の支持体として広く知られていますが、アクリル絵の具との相性はかなり良いです。
キャンバスは元々、帆船の帆布に下地材を塗って使用されはじめたと言われており、適度に弾力性や布特有のボコボコ感があります。
描く前でも後でも、アクリルガッシュのような割れやすい絵の具で描いていない限り丸めて保管しておく事もできます。
アクリル絵の具でキャンバスに事に向いている作風

キャンバスに描く事でより本格的な絵画感が出ます。
(海外では描いてから木枠に張る場合も多いですが)木枠に張っていない状態で比較的コンパクトな状態で丸めて持ち運びができます。
基本的にはどんな描き方や作風にも対応する事が可能です。
デメリットとしては木枠に張って描いていると手の圧力などで張りが緩くなってたるんでくる点とアクリルガッシュで描いた場合、キャンバス表面を歪ませた時に割れてくる可能性があります。
キャンバスを選ぶ際に絵の具と下地の相性の関係で注意点があるので以下に書いていきたいと思います。
キャンバスの下地の種類とそれぞれの特性
先ほど書いたようにキャンバスは一般的に布でる作られているので、下地処理をしなければ布に絵の具がしみ込んだりボコボコしすぎていて非常に描きにくいです。
そのため、販売されているキャンバスの多くは下地処理されたものがほとんどですが
その中でも使用する絵の具によって向き不向きのある以下の三種類の下地があります。
エマルジョン下地
キャンバスの下地の中では最も一般的な下地の種類で多くの市販キャンバスに使用されている下地です。
水性絵の具と油性絵の具の両方に対応しているのでアクリル絵の具には特に適した下地になります。
水性下地
水性下地は吸収力が高く、油絵の具で描くと油分を吸収しすぎて亀裂が入る可能性があります。
厚塗りはあまり向いていませんが、水性絵の具で描く事に向いています。
油性下地
油性下地は主に油絵の具用の下地として使用されます。
アクリル絵の具を含めた水性の絵の具は塗っても剥がれてくるので適していません。
アクリル絵の具に適した下地のキャンバスを購入したい場合は、油性下地かどうかの部分を確認しましょう。
キャンバスの目の粗さの種類
キャンバスにはメーカーによって多少の違いはありますが、布の目の粗さによって荒目、中目、細目の三種類が存在します。
特にこだわりが無ければ中目を使用する事で問題無く制作できます。
荒目などはダイナミックで力強く、布の目を生かして制作したい時に向いています。
細目は中目に比べて目が細かく、平滑で細密な表現に向いていますが中目を使用していても下地材(ジェッソ)を自分で後から塗って滑らかさを調節する事は可能です。
次に紹介する木製パネルは最初から平滑な画面なので状況によって使い分けても良いかもしれません。
アクリル絵の具で木製パネルに描く場合
木製パネルは、キャンバスや紙よりも硬くて丈夫な支持体になります。
木製パネルはキャンバスのような織目が無いのでより平滑で繊細な表現が可能になります。
基本的に販売されている木製パネルは下地処理のされていないものがほとんどなので、買ってから自分で別に用意したジェッソを塗る必要があります。
アクリル絵の具はほぼ何にでも描く事はできますが、ジェッソを塗る事で発色も描きやすさも格段に良くなります。
シナベニヤパネルとラワンベニヤパネルの特徴
画材屋で制作用として販売されている木製パネルには主に、シナベニヤパネルとラワンベニヤパネルの二種類があります。
シナベニヤパネル
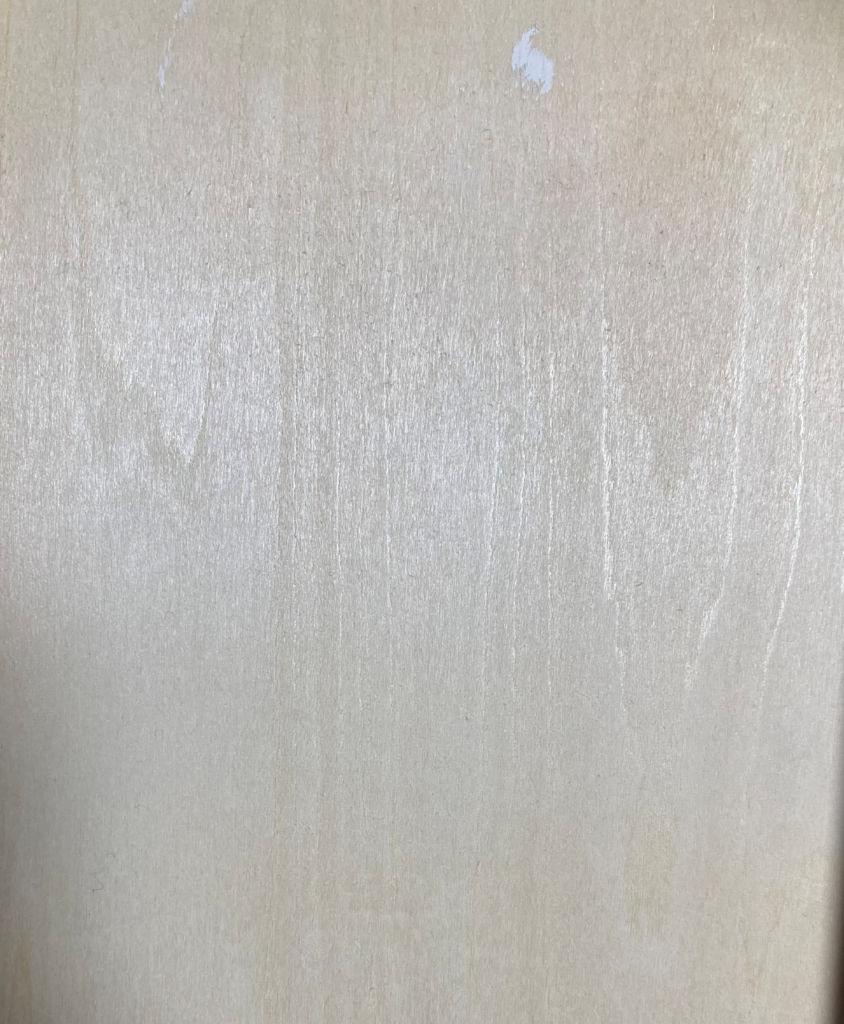
木製パネルにアクリル絵の具で絵を描く場合は基本的にはシナベニヤパネル一択で良いかと思います。
木特有の木目やボコボコ感も少なく、かなり平滑なのでジェッソを塗る事でより細密な描き方も可能になります。
木に描く時の注意点として、制作後に絵が黄ばんでしまう可能性のある木のヤニを処理する必要がありますが、シナベニヤパネルは比較的ヤニの出にくいので簡単に使用する事ができるのでおすすめです。
シナベニヤパネルのデメリットとしては次に紹介するラワンベニヤパネルに比べて価格が高い傾向にありますが、店舗によって価格は少しずつ異なってきます。
関西でかなり安く画材を購入できる画材屋さん紹介記事↓
ラワンベニヤパネル

絵画制作用木製パネルにはシナベニヤと並んでラワンベニヤパネルがあります。
シナベニヤパネルに比べてやや価格が低い傾向にあります。
デメリットとしてはラワンベニヤパネルはシナベニヤパネルに比べてヤニが出やすくヤニ止めを塗らないまま薄めのタッチで制作すると後になって作品が黄ばんでくる可能性がある事と画面が木目で少しボコボコしています。
そのまま処理せずに使用するとせっかく描いた作品が変色してしまう原因にもなりかねないのでどうしてもラワンベニヤパネルを使用する場合はヤニ止め剤を塗ったりジェッソで表面を平滑に使用する事をおすすめします。
主に紙を水張りして描く用に向いているかなという印象です。
処理が面倒という人は価格もほぼ変わらないシナベニヤパネルを選んでおけば問題ないと思います。
最後に
今回は「アクリル絵の具は何に描く?初心者向け:紙、キャンバス、木製パネルの選び方と特性」のテーマでお伝えしてきました。
同じ絵の具と描き方であっても支持体が違うと見え方も変わってきます。
ここでは主な支持体の紙、キャンバス、木製パネルの三つについて書きましたが、紙一つを挙げても画材屋さんには一回では目を通しきれない程の種類の商品が並んでいます。
自分にあったものを見つけるために画材選びを楽しんでみる事も良いアイデア出しにも繋がるかもしれません。
最後まで読んで頂きありがとうございました。



