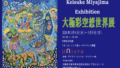こんにちは、画家の宮島啓輔です。
目次
作品を言語化するとは?言葉で作品を補う考え方
アートは、本来言語だけではできない事のできる表現でもあります。
だからこそ、言語化せずヴィジュアルだけを提示する良さも確かに存在します。その為、「作品の多くは語らない方が良い」という意見を持つ人も多いと思います。
しかし、「言語(文脈)」をつける事によって「アート」ができる事の幅が増えると私は考えます。
実は、この「言語(文脈)」は、大昔の絵画から現代アートにおけるまで、かなり重要な役割を持っています。
例を挙げると、「聖書の文脈をもつ最後の晩餐」や「波乱万丈な人生を歩んだゴッホが描いたひまわり」、「反戦というメッセージを持つピカソのゲルニカ」等々、背景情報があるからこそ価値を生んでいるパターンはいくつもあるのです。
作品単体だと目にとまらないものでも、「芸能人が描きました!」と説明されると見入ってしまう事もその一つです。
この記事には、作品を言葉にする方法が気になって読みに来てくださった人が多いと思うので、「作品を言語化する事」に関する私が実践している具体的な考え方などを今思いつく限りをお伝えしていきたいと思います。
ここでは、絵本が文脈ありきで成り立つ事が多いように、「作品を言葉で補う考え方」を感じて頂きたいと思います。
世界観を言語化する際に必要な考え方
作品をいきなり0→1で言語化するとなっても、難しいと思う事が多いです。
それは、今、頭の中で取り出せるアイデアだけで言語化をしようとすると、手札が限られている為いつか限界がきてしまいます。
何かに時間をかけて取り組む時は、ほとんどの場合がそうですが、段階を踏みながら立ち止まって試行錯誤したり、判断の為に必要な情報をつぎ足しながら進める必要があります。
何かが降ってきたように手や頭を動かす事のできる人やパターンもありますが、基本的には細分化して段階を踏む事は避けて通れません。
また、そうする事でスタートラインでは思いつきもしなかった事に順を追う過程で気づく事もできます。「こんな所に自分は興味があったんだ」や「自分はこの描き方が好きだ」等々、、。
描きながら徐々に文脈を手繰ったり、少しずつ考えを巡らせながら進める事も大切なのです。
少し抽象的な表現になりますが、自分自身と対話したり、自分の中の要素を引っ張り出してくる行為でもあるんですね。
作品を言語化する3つのタイプ
ここでは、3つの言語化パターンを紹介しますが、個性や創作に対する人それぞれの考え方によって異なってくるので、あくまで私の思いつく限り、いくつかの角度からの言語化タイプを整理してみます。
自分はどの言語化タイプが合っているかを思い浮かべながらから確認してみてください。
なぜ描いたのかを掘り下げる内省型
これは、自分の感情や動機の部分を掘り下げて言語化するタイプです。
作品の「描くきっかけ」「創作の衝動」などの、作家個人の心を掘り下げる方法になります。
私は、最近アジア旅中で影響を受けたものを現地でそのままペン画にする作品シリーズを始めたのですが、これも「旅中で観たものに心を動かされたから」のように言葉に落とし込む事ができます。
自分自身の感情を軸と捉えて、その軸がどう動いたかや何を辿ってきたかを言葉にするイメージですね。
南瓜や水玉アートで知られる有名芸術家の草間彌生さんを例に出してみます。
草間彌生さんは、幼少の頃から水玉や網目が襲ってくる幻視幻聴等の統合失調症の症状に悩まされていました。
そこで、救いを求めて辿り着いたのが創作活動だったそうです。見えた水玉や網目の反復をあえて絵に昇華する事で、病気に立ち向かったと語られています。
これも、自分の内部を言語化する例のひとつと言えます。
ここまで、大きな例で無くても「調子が良かったから」や「画材屋で画材を眺めていて描きたい欲がわいてきた」等もこのタイプに当てはまります。
この後に紹介する言語化パターンと重なる場合も多いと思います。
ただ、描いた理由と言っても「漠然と描きたかっただけ」という人もいると思うので、他パターンを整理してみます。
絵の中の感覚、感情を言葉に変える感覚変換型
これは、絵の雰囲気や感覚を、詩のように絵にのせるタイプです。
絵本や詩画集をイメージして頂けるとわかりやすいかもしれません。
多くの人が知っている言葉で例を考えてみます。
有名な松尾芭蕉の俳句に「古池や蛙飛び込む水の音」があります。
静寂の中でカエルが水に飛び込む事で、その静けさが際立つという情景が思い浮かぶ解釈をされる事が多いですが、この句に寂れた池や、淡い緑を使った絵を融合させてみる事で、より豊かなイメージで表現する事ができます。
言葉と絵はどちらが先でも良いですが、詩的に観た人に感覚を届けるタイプの言語化は、詩や物語の挿絵に近い要素があります。
空気・光・温度感・匂いなどに着眼してみても良いかもしれません。
私は、あまり自分の作品に使用するタイプでは無いのですが、この言語化タイプは既存の詩からヴィジュアルをイメージしたり、その逆で、絵→詩の作業を頭の中で反復してみる事で、より解像度が増すと思います。
自分の世界観を整理する構造型
先述の内省型、感覚変換型と名付けたタイプの延長線上にある自分の作品やテーマにどんな傾向や要素があるのかをまとめるタイプです。
私であれば、このサイト名でもある極彩色な空想の世界を描いた絵を短くして「極彩空想世界」をキャッチコピーのように名付けています。
また、他の例では作品に描かれたモチーフや模様に込められた意味やコンセプトを言語化する等です。
少し定義が広すぎるので具体例を挙げると、キリスト教絵画などにおいて、登場する人物や神が持つ持ち物からその意味や役割が読み取れるものです。例えば、聖母マリアは、ウルトラマリンブルーのマントを着ていたり、キリストの肉と血の象徴をパンとワインで表現したり等々、これをアトリビュートと言います。
実際に、実践する際はこの例のような宗教的な象徴である必要はありませんが、「こんな作品や話のオマージュです」や「この空間や模様には、自分はこんな思想や思いを込めています」等もこれに該当すると思います。
社会的なメッセージや何かを訴える手段としてのアート作品もこれに含まれると思います。
ストーリー性やどんなコンセプトなのかについて言語化するこの構造型は、より、その傾向の強い世界の美術史に触れると、着想が得やすくなります。
最後に
ここまで紹介した3つの言語化タイプの中に、多くが当てはまるのではないかなと思います。
ただ、定義が抽象的で広すぎて理解しにくいという人がいるかもしれません。
古今東西を問わず、多くの作家や作品、その解釈について触れてみる事で、より解像度があがり、自分の手札は上がる事と思います。
今回は、【【作品を言語化する力】アートの世界観を言葉にする方法】のテーマでお伝えしてきました。
創作の言語化の際のヒントになれば幸いです。
他記事で、アートのコンセプトについての記事も公開しているので是非読んでみてください。
最後まで読んで頂きありがとうございました。