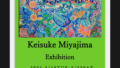こんにちは。画家の宮島啓輔です。

私は現在まで細密で極彩色な世界観の作品を制作し、コンテストや公募展などでは十年で五十個弱ほどの主な受賞をしてきました。
細かい受賞歴等はこちら↓
今回は、「画家になるには公募展やコンクールへの出品・入賞は必要なのか?意義や構造・良し悪しなど」のテーマで書いて行きたいと思います。
私は絵を描き始めたばかりの頃から頻繁にアート関連のコンペなどへの出品を繰り返してきたのですが
とりあえず出品しておけば、どこかの誰かに見つけてもらえるんだと半ば他力本願な考えで行動していた時期がありました。
絵を描く方にとっては一個の目指すべきところと世間では考えられているアートコンペですが私は少しずつ時間を重ねてそのような状況を考えていくと少し自分がアートコンペなどの意義等に対して少し勘違いしているところがあることに気づいたのです。
最近もたまに絞って出品はしていたりするのですがその部分も含めて今回の記事では実際アートコンペがどういったものかや私の考え方などを書いて行きたいと思います。
画家にとってコンクールや公募展出展の意義
現代で活躍されている著名なアーティスト方たちの経歴や売れ始めた様々なきっかけなどを観ると
「~賞受賞をきっかけに名が知られて」
のように権威のある受賞歴などが書かれていることがあります。
このような受賞歴や堅いアート団体への所属、何々先生の師事などの肩書を元に有名になって活躍されている方は一部実際に存在しますがそこの下にはそのコミュニティ内での競争に敗れた人たちがたくさん背景にいるのです。
もちろんアートコンペ等での受賞をきっかけに知名度を得て、いい画廊や企業と契約してそれが継続し、成功されている方、自分のブランド価値を上げる事などに上手く利用している方はいらっしゃいます。
ただ、画家として知名度を誇り活躍している人の経歴は様々ですが、特に世に名の知れている方たちは業界内での強さと独自性などを持って複数の苛烈な戦いを潜り抜けた人も多く、このような一つのコンテストだけを成功方法への目標とすることは難しく稀なのです。
一部の点を取ればそのような成功例があるのかもしれませんが、どのみちそこから本格的な画家としてステップアップをして行くには「アートコンペ」自体は入り口の役目となります。
また日本のアート業界には文学界での芥川賞のような世間での知名度も高く受賞するとこれからの作家人生がほぼ保証されるような賞はあまり存在しません。
このような「アートコンペ」や「画壇」のような道のりだけを歩まなくとも成功されている画家の方はたくさんいますし仮に運よく受賞からの活躍への入り口が見つかったとしてもそこから可能性を膨らませて実行して行く力量や運の要素が必要になります。
公募展・美術団体展示の構造
私は出品料のかかるコンペ等にはほぼ出していませんが、世の数あるアートコンペに参加しようと思うとお金がかかる事が多いです。
もちろんこのような公募展や美術団体が運営するような展示会もビジネスなので審査員を頼む費用や会場費としてお金が必要になります。
もちろん善良でオープンな審査や展示が行われそれなりのリターンのあるところも多く、それで出品者も主催者も納得して運営されているところもあります。私が最近受賞したところは作家へのリターンがかなり良いところでした。
ただ、お金や派閥、階層などが渦巻き、そのような本来の絵以外の要素で審査が決められるというような黒い噂があり、現在もその体系が存在しているという噂があることも事実です。
団体の上の人たちは入って間もない人たちから会費を納めさせて懐に入れたり、最悪の場合納め続けた年数や派閥、コネを基準にその団体から賞を与えるという仕組みなので所属して得られるものというと知っている人にのみ通じる権威と経歴が一行増えるくらいです。
人それぞれの目的によりますが、コミュニティ内に所属している事自体やそこでのコミュニケーションが楽しいという場合や出品料は必要だとしてもオープンな審査で作家へのメリットが大きい公募展など良い部分ももちろん存在するので完全否定をしているわけではありませんが、気になる場合は事前に審査基準や過去の運営構造や評判を調べて吟味する事も一つの手かもしれません。
画家が活用できる良い公募展
公募専用サイトが存在するほど数ある公募展の中には絵を描く人にとってメリットがある公募展も存在しています。
出品料無料のものであっても選考の結果入賞することで名の知れた画廊で個展が開ける権利を得ることができたり、主催メーカーの画材を贈呈されたり、色んなコレクターの集まり著名な作家による審査があったり等々画家にとってメリットの大きい公募展もいくつかあります。
作品制作や発信の手助けとなる公募展には挑戦してみることも良いかもしれません。
もちろんその公募で求められるレベル以上の作品を作る必要があり落選になる事もありますが、自分の作品をその審査員の尺度に落としこんで審査され、それなりのメリットある目標獲得を目指すという事も一つの行動ではあります。
またそのような経歴などが無くとも画家として活躍されている方はたくさんいますが、受賞などの少し堅めの経歴・肩書、またはその時の写真などを持って置くことで画家としてのイメージを補助的に見せることもできます。
最後に
先程も書きましたが公募展を活動に生かしたいとする場合、
コンテスト入賞→ギャラリーや画商から目が留まる→画商やギャラリーに絵を売ってもらう →画家として活動を展開して行く
のような多くの人がイメージする作家人生で活躍されている例は存在しますがどの場合であってもそのような経歴を生かして先の未来を膨らませるかが一番大切になります。
対象としている公募展への出品・入賞が予想できる範囲で自分にとってどのくらいのメリットや効果があるかを視野に入れて挑戦する事が重要だと言えるでしょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。