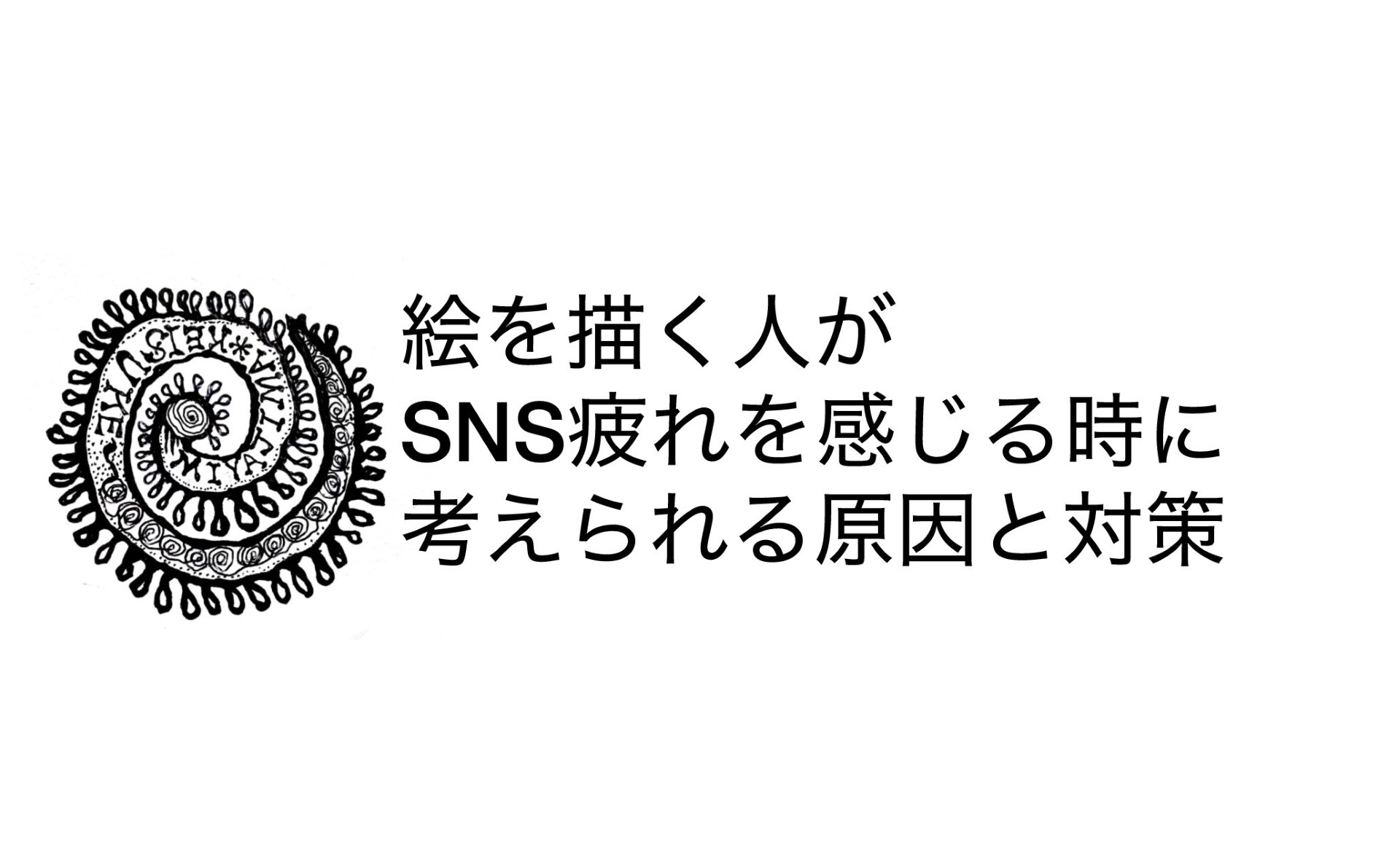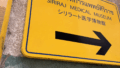こんにちは。画家の宮島啓輔です。

絵を描く人をはじめ、日本国民の半数以上が見る側から発信する場まで利用しているSNSですが、便利な反面、心が疲れてしまっている現実がよく聞こえてきます。
今回は、「絵を描く人がSNS疲れを感じる時に考えられる原因と対策」の内容でSNSへの向き合い方へのヒントについてお伝えしてければと思います。
SNSで心が疲れる主な原因だと思う事
SNS疲れにはさまざまな理由がありますが、絵描きの多くが感じているのは「比べること」による疲れではないでしょうか。
これは、投稿そのものから得られる情報と自分を比べる事も含まれますし、単純にネガティブな内容を自分に取り込んでしまって共感疲労するという事もあります。
他にも個人間でのトラブルなど色々あると思いますが、特に比べる事が私の周りの絵描きの人の話を聞いていても多いように思います。
反応が思ったより少なかったり、常にタイムラインに他の人の投稿が目に入るのを見て気づいてない間に他人を自分の土俵に取り込んでしまっている事があるのです。
絵や活動にはそれぞれのベクトルがある
この自分と他者を同じ土俵にいると考える原因は、「上手い下手」や「フォロワー数」などの一律のものさしを全員に当てはめて考えている事にあります。
実際、絵にはその作者の数だけものさし(ベクトル(方向性))が存在します。
写実的な描写が得意で写真のように描ける人もいれば、色彩感覚で魅せる人もいます。
デッサンが完璧でなくても、ゆるいイラストで心を掴む人もいます。フォロワー数においては、万人受けしていて数千人のフォロワーがいる人もいれば、数百人でも濃いフォロワーがいる人もいます。
この方向性については、部分的にピックアップした比較ができても、他者と完全に同じものさしに同調させることは、他者と自分が別の存在な為、不可能です。
異なる方向性同士を単純な優劣で比べる子tにあまり意味はないのです。
比べる事の唯一の利点は自分に取り込める事
勿論、比べる事によって得られるメリットもあります。
比べるというよりも、インプットに近いものかもしれません。
他人の創作物をみて、すごいと思ったり自分ならこうするなと思える魅力や視点を発見する事自体は、自分の作品や活動に取り込む事は、比べる事の唯一と言っていいほどの大きな利点です。
自分と相手に完全に同調したものさしで比べる事はあまり望ましい事ではありませんが、自分のものさしに相手の要素を盛り込む事で成長に繋げて行く事ができます。
SNSが向いてないかもしれない
冒頭にも書きましたが、SNS疲れには色々な原因がありますが、そもそもSNSそのものの特性や全体の流れがあまり自分に合っていないという可能性もあります。
突然アカウントを離れたりすると日常との落差が大きく影響が大きくなりますが、自分に合った距離感に調節していく事もひとつの選択肢です。
SNSを使う事が全ての発信や共有の場ではないかなと義務感を外して考えると気持ちは少し軽くかもしれません。
最後に
今回は、「絵を描く人がSNS疲れを感じる時に考えられる原因と対策」の内容でお伝えしてきました。
SNSは魅力や学びを得られる場所でもあり、デメリットも併せ持つ場所でもあります。また、理屈ではわかっていてもどうしても感情面で疲れるという事もあると思います。
本記事の内容が全てではありませんが、少しでも読んだ人のお役に立てれば幸いです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。